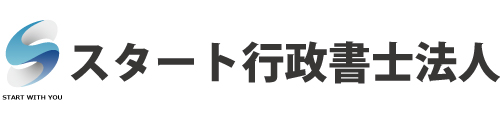建設業許可・経営事項審査・入札指名願
入札参加資格審査申請(指名願)について
建設業許可申請
-
どんな場合に許可が必要?
-
建設工事の請負を業とする者(個人・法人)は、元請・下請にかかわらず、適正施工・発注者保護の観点から、建設業許可を受ける必要があります。但し、1件の工事請負代金が500万円未満(建築一式工事の場合には1500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)の場合、小規模工事の扱いとなり建設業許可は不要とされています。
もちろん、小規模工事しか業としない場合であっても許可を受けることは可能ですので、お問合せ下さい。
-
どんな業種があるの?
-
次の表のとおり、29の業種が建設業法で定められており、業種ごとに許可を受ける必要があります。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業
※御社の業種がどれにあたるのか不明な場合はお問合せ下さい。
-
大臣許可と知事許可ってどう違うの?
-
まず、許可行政庁が「国土交通大臣」か「都道府県知事」かで区別されます。では、この区分の違いは何かというと、単純です。建設業を営もうとする営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。また、営業所が1箇所のみの場合、都道府県知事許可を受ける必要があります。
例)大阪府東大阪市に営業所が2箇所
→大阪府知事許可
例)大阪府東大阪市と大阪府堺市にそれぞれ営業所あり
→大阪府知事許可
例)大阪府東大阪市と兵庫県尼崎市にそれぞれ営業所あり
→国土交通大臣許可
例)北海道と東京都と沖縄県にそれぞれ営業所あり
→国土交通大臣許可※国土交通大臣許可申請は、本店所在地の管轄都道府県を経由して、地方整備局長宛てに行います。
※同一の都道府県内であっても2箇所以上の営業所において建設業を営もうとする場合は、営業所ごとに許可が必要です。
-
一般建設業許可と特定建設業許可って何?
-
先程の29業種のうち、営業しようとする業種ごとに「一般建設業許可」または「特定建設業許可」を受けなければなりません。
発注者から直接請負う工事について、自社ですべて施工する場合においては法律の規制はありません。つまり、自社が元請で自社で施工する場合や、下請負人として工事を請負い自社が施工する場合は、金額に上限はありません。
問題となるのは、自社で全てを施工せず、一部を下請業者に出す場合です。その際、下請に出せる金額によって「一般建設業」と「特定建設業」に区別されます。その金額とは次のとおりです。一般建設業許可 建築工事業以外の場合 4000万円以上(税込み)の工事を下請に出すことはできない。 建築工事業の場合 6000万円以上(税込み)の工事を下請に出すことができない。 特定建設業許可 全ての業種 下請に出せる金額に定めなし。 注)参照 注)但し、特定建設業許可業者であっても「一括丸投げ」をすることはできませんのでご注意下さい。
例)6000万円の土木一式工事(道路改良工事)を請負って、とび・土工工事業者に1300万円、舗装工事業者に2500万円、管工事業者に500万円(合計4300万円)を下請させるには4000万円以上なので、特定建設業許可がないとできません。
例)8000万円の建築一式工事(一戸建て注文住宅)を請負って、大工工事業者に2000万円、内装仕上工事業者に1800万円、電気工事業者に1000万円、管工事業者に1000万円、左官工事業者に500万円、屋根工事業者に500万円(合計6800万円)を下請させるには6000万円以上なので、特定建設業許可がないとできません。
※上記の金額は、1つの請負工事金額のうち、下請に出せる金額の合計額です。
-
許可の有効期間
-
建設業許可には有効期限があり、許可日から5年間有効です。例えば令和3年1月1日が許可日の場合、令和7年12月31日で許可の有効期間が満了します。引き続いて建設業を営む場合は、更新の申請手続が必要となってきます。 更新手続は、許可期限の30日前までにしなければなりません。先の例で言うと、令和7年12月1日までに更新手続を終える必要があります。また、この更新申請は、許可期限満了日の3ヶ月前から行うことができます。
-
許可の要件
-
建設業許可を受けるには、大きく分けて次の6つの許可要件をクリアしなければなりません。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
建設業に関し、一定の経験を有する者(常勤役員等1人もしくは常勤役員等1人+当該常勤役員等を直接補佐する者)を配置し、適正な経営体制を確保することが必要です。 建設業の経営は、他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について、一定期間の経験を有した者が最低でも1人又は経営業務の管理を適正に行うに足る体制が必要であると判断され、この要件が定められたものです。
※ 許可を取得した後に、経営業務の管理責任者が退職等により、後任が不在となった場合は、 要件の欠如として許可の取消しとなります。(法第29条第1項第1号)
●「常勤役員等」とは
法人である場合:役員のうち常勤であるもの。
個人である場合:その者又はその支配人。〇「役員」とは
・業務を執行する社員 → 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
・取締役 → 株式会社の取締役
・執行役 → 指名委員会等設置会社の執行役
・これらに準ずる者 → 法人格のある各種組合等の理事等
※「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれませんが、 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、 取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれます。
※執行役員の経営業務の管理責任者については、事前に個別の認定が必要になります。〇「常勤であるもの」とは
原則として主たる営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、 その職務に従事している者をいいます。●「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人、 その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験を有する者をいいます。
●建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を個人で満たす場合は、以下のとおりです。
経営経験 建設業の経営経験 経営期間の地位 〔経営業務の管理責任者〕
役員、事業主、支配人、支店長、営業所長等(営業取引上対外的に責任を有する地位)〔経営業務の管理責任者に準ずる地位〕(※)
役員又は事業主に次ぐ職制上の地位〔経営業務の管理責任者に準ずる地位〕(※)
役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位経験内容 経営業務の管理責任者としての経験 執行役員等としての経営管理経験(a) 経営業務を補佐した経験(b) 必要経験年数 5年 5年 6年 根拠法令 ・規則第7条第1号イ(1) ・規則第7条第1号イ(2) ・規則第7条第1号イ(3) ※ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」の経験とは ・・・
(a)執行役員等としての経営管理経験
業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあり、取締役会設置会社において、取締役会の決議に より特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験
(b)経営業務を補佐した経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、 技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について従事した経験(6年以上必要)
また、「準ずる地位での経験」の場合は、事前に個別の認定が必要になりますので、十分な期間をもって、事前にスタート行政書士法人にご相談下さい。
(注)詳しい内容については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)を参照してください。
●建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる経験を体制で満たす場合は、以下のとおりです。
①の経験に加えて②又は③の経験を有する 常勤役員等が1名
+ ④、⑤、⑥の経験を持つ当該常勤役員等を直接 に補佐する(※)者をそれぞれ1名ずつの3名 ①建設業に関し2年以上の役員等としての経験 ④その会社での5年以上の財務管理の業務経験(※) ②建設業に関し、3年以上の役員等又は役員 等に次ぐ職制上の地位(※)にある者(財務管 理、労務管理又は業務運営の業務を担当する 者に限る)の経験 ⑤その会社での5年以上の労務管理の業務経験(※) ③3年以上の役員等の経験(他業種も可) ⑥その会社での5年以上の業務運営の経験(※) ※ 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは ・・・
申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。※ 「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務経験とは ・・・
(a)財務管理の業務経験 建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいう。
(b)労務管理の業務経験 社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいう。
(c)業務運営の業務経験 会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいう。 上記の経験は、許可の申請を行っている建設業者及び建設業を営む者における経験に限られます。※ 「直接に補佐する」とは ・・・
常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいう。
(注)常勤役員等を直接に補佐する者が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る常勤役員等を直接に補佐する者を兼ねることができます。 また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えないものとして取り扱います。「役員等に次ぐ職制上の地位にある者」、「当該常勤役員等を直接に補佐する者」の場合は、事前に個別の認定が必要になりますので、十分な期間をもって、事前にスタート行政書士法人にご相談下さい。
②適切な社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入している者であること
法令上加入が義務付けられている保険に加入していない者は適正に経営を行っているとはいえないため、適正な経営を行うことができることを要件とする法第7条第1号の基準として規定するものです。
具体的には、次のいずれにも該当する者であることを要件とします。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業に該当する全ての事業に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条の規定による届書を提出した者であること。
※「営業所」とは、建設業法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所をいいます。)③専任の技術者を有すること(専技)
許可を受けようとする営業所には、業種ごとに国家資格等を有する専任の技術者を置かなければなりません。一般建設業と特定建設業とでは、要件が異なりますので次表を参照下さい。
一般建設業の 許可を受ける場合 イ
国が定める学科の高等学校を卒業+卒業後5年以上の実務経験
国が定める学科の大学を卒業+卒業後3年以上の実務経験
ロ 10年以上の実務経験 ハ 国が定める試験の合格者(有資格者) 特定建設業の 許可を受ける場合 イ 国が定める試験の合格者(有資格者) ロ
上記一般建設業の要件イロハのうちいずれかに該当する者で、許可を受けようとする業種を直接請け負い、その請負代金が4500万円以上であり、且つ2年以上の指導監督的実務経験を有する者 ハ 国土交通大臣が認定した者(大臣認定) ※以上のいずれかに該当することが必要です。但し、上記以外にも例外がありますのでご相談下さい。
※以上は全て、許可を受けようとする業種に対応したものでなければなりません。
※同じ資格でも、一般と特定では許可を受けられる業種が異なる場合があります。④財産的基礎又は金銭的信用を有すること
一般建設業許可を受ける場合 特定建設業許可を受ける場合 次のいずれかに該当すること 次のすべてに該当すること 1 自己資本額が500万円以上であること 1 欠損の額が資本金の20%を超えないこと 2 500万円以上の資金調達が可能であること 2 流動比率が75%以上であること
3 許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること 3 資本金額が2000万円以上で且つ、自己資本額が4000万円以上であること ⑤単独の事務所を有すること
申請者が所有または賃貸することにより、建設業を行う事務所を有していなければなりません。
他の会社と同一敷地内または同一フロア内に事務所を構える場合、場所が明確に区分されている必要があります。
自宅等を事務所にする場合、居住スペースと事務所が明確に区別されている必要があります。⑥欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは次のとおりです(抜粋)。
ア)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ)不正手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
ウ)許可の取り消し処分を免れる為に廃業届を行い、その届出日から5年を経過しない者
エ)営業停止期間が経過しない者
オ)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終え、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
経営事項審査申請(経審)について
-
どんな業者が申請できるの?
-
官公庁(国土交通省の機関や都道府県、市町村、その他外郭団体等)から、直接公共工事を受注したい業者が申請できます。 逆に言うと、官公庁から直接建設工事を請け負いたい業者は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。
当然建設業許可の取得が最低条件となります。
-
そもそも経営事項審査(経審-ケイシン)って何?
-
先程述べたとおり、公共工事の入札に参加することを希望する業者が申請するわけですが、この申請は「工事の施工能力」「財務の健全性」「技術力」等を総合的・客観的に評価してもらう為に行います。具体的にいうと、経営事項審査申請(経審)とは、申請者である建設業者に対して通知簿のような点数を付けて貰う作業ということになります。申請書類の正式名称は「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」と呼ばれています。
-
審査基準日って何?
-
審査基準日とは、経営事項審査申請をする日の直前の事業年度末日(いわゆる決算日)のことを言います。
だだし、新規申請の場合など、建設業許可日が審査基準日となる場合や、新規に法人設立をした際の設立日をもって審査基準日とする場合がございますので、申請可能か不明な際はご相談下さい。
-
有効期間ってあるの?
-
経営事項審査申請は一度すれば一生ものという訳ではございません。
当然の事ながら、会社の状況はめまぐるしく変化するものなので、常に最新の情報がないと役所もどの業者に発注してよいものか判断することができません。そのため、経営規模等評価結果通知書には有効期間というものが設けられています。この有効期間は審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。ですので、有効期間が満了するまでに経営事項審査の継続(更新)申請が不可欠となります。
例えば、令和2年1月31日が審査基準日の場合、結果通知書の有効期限は令和3年8月31日までとなります。つまり、令和3年8月31日までに次の審査基準日である令和3年1月31日時点での経営事項審査申請を終え、且つ結果通知書が手元になければ、令和3年1月31日基準日の結果通知書が来るまでの間に空白期間が生ずる事になります。スタート行政書士法人では、こういった企業様の管理(いつまでに申請しないといけないか等)を行っていますので、ご安心下さい。
-
何を審査されるの?
-
経営事項審査の審査項目等は次のとおりです。
項目区分 審査項目 最高点 最低点 ウエイト 審査機関 経営規模等 経営規模 X1 完成工事高(業種別) 2,309 397 0.25 許可行政庁 X2 自己資本額 利払前税引前償却前利益の額 2,280 454 0.15 技術力 Z 技術職員数(業種別) 元請完成工事高(業種別) 2,441 456 0.25 の他の 審査項目 (社会性等) W ①労働福祉の状況
②建設業の営業継続の状況
③防災活動への貢献の状況
④法令遵守の状況
⑤建設業の経理の状況
⑥研究開発の状況
⑦建設機械の保有状況
⑧ISOの取得状況
⑨若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況1,966 -1,995 0.15 経営状況 経営状況 Y ①負債抵抗力
・純支払利息比率
・負債回転期間
②収益性・効率性
・総資本売上総利益率
・売上高経常利益率
③財務健全性
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
④絶対的力量
・営業キャッシュ・フロー
・利益剰余金1,595 0 0.20 登録経営状況分析機関 ★ 総合評定値(P)は、次の算式により算出します。
総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)
総合評定値(P)の点数
最高点 : 2,143 最低点 : -18
-
うちの会社は何点ぐらいになるの?
-
当行政書士法人では、経営事項審査のシミュレーション(初回は無料)を行っておりますので、申請前に点数をお知りになりたい業者様は、お気軽にお申し付け下さい。
→経審シミュレーションを希望する
入札参加資格審査申請-指名願-について
-
入札参加資格審査申請-指名願-
-
建設業許可を得て、経営事項審査を受け、経審の結果通知書を手にした業者が、公共建設工事の受注を希望する役所へ申請します。この申請により、それぞれの役所が公共工事を発注できる業者名簿に、認定の上登録されます(役所により体裁は異なります)。原則として登録の有効期間は1年から4年程度で、有効期間満了前に更新(継続)手続を行います。
この様に、入札に参加することができる資格を持つ業者名簿に記載されれば、あとは営業をして実際の入札に呼ばれることを待ちます。その後、見事落札でき、役所の求める手続(履行保証等)を行い、契約が完了すれば、役所の元請業者として建設工事を行うことができます。
地域的な条件や発注予定工事の有無によって、建設業者が受注でき得る可能性は異なりますが、できる限り多くの官公庁に希望を表明(入札参加資格審査申請)する方が当然受注の確率は高くなります。
ただし、申請書に添付する納税証明書や登記簿謄本・印鑑証明書などの実費がかかること、また、当方の報酬が掛かることを十分考慮されたうえで投資を行ってください。
近畿地方整備局HPより引用
※役所により、申請時期や書類、要件等が異なりますので、詳細はスタート行政書士法人までお問い合わせ下さい。